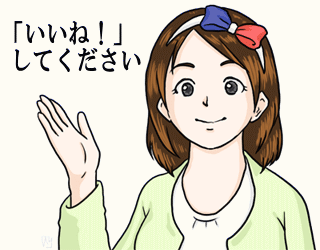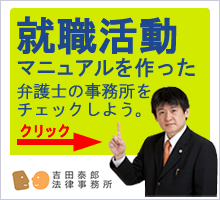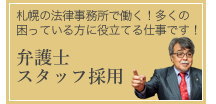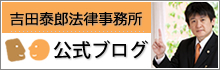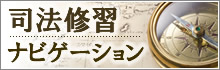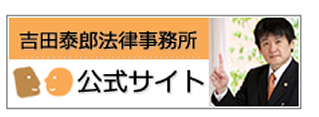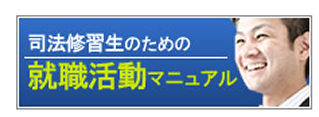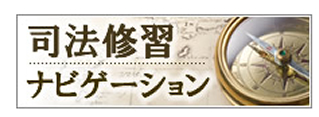なぜ面接をするのか

なぜ面接をするのか
アルファにしてオメガの問題なのであるが、そもそも「採用側がなぜ面接をするのか」ということである。
法律事務所の面接に限らず、就職活動には必ず面接という過程が存在している。
なぜ、社会では手間ヒマかけて面接をするのだろうか?
なぜ、試験だけで採用を決めないのであろうか?
そこにはやはり、試験で計測することは難しいこと、面接でなければわからないことが存在するからだ。
面接を受けるときに、「みんながやっているから面接を受ける」というように、何も考えずに、ぼーっと面接を受けているのか。
それとも、面接がなぜ存在するのかという深いところから、自分なりに考えたうえで面接を受けているのか、ということである。
もちろん、自分なりに考えて受けた方がよい。
結論からいえば、採用側としては、面接の最終的な目的は
相手がどういう人間なのか、ということを理解する
ということである。
「どういう人間か」というのは、じつはとても深い話なのだが、ここでは人間の深淵の話については、とりあえず置いておこう。
目の前の問題としては、「採用するのか、しないのか」という観点から考える「相手がどういう人間なのか?」という問いである。
したがって、採用との関係においての人間の評価基準を論ずれば足りることである。
採用との関係においての評価基準は、意外とそんなには多くはない。
1、礼儀をわきまえた人間かどうか
どんなに試験の点数が良かったとしても、無礼な人間を採用しようとは全く思わないものだ。
ここで言う礼儀には、
●お辞儀の角度が適切かどうか、
●相手の顔を見て話しているのかどうか、
●言葉づかいがきちんとしているかどうか、
●姿勢が良いかどうか、
そういう形式的な礼儀も当然含まれる。
また、
●話している相手に敬意をもって話しているかどうか、
●自然な気遣いがあるかどうか、
●正直かどうか、
●他人の悪口になるようなことを言うのか言わないのか、
そういう実質的な意味での礼儀も含まれる。
形式的に言葉づかいだけが丁寧であっても、相手を見下している態度だと「慇懃無礼」と言って、これはこれで無礼なのだ。
大学や司法研修所では、礼儀作法について、ことさらに学ぶ機会は少ないのかもしれない。
しかし、礼儀作法がきちんとしているかどうかは、実社会では、とても大事なことである。
就職活動をする前に、一度はビジネスマナーの本を読んで勉強するべきである。
まともな面接官であれば、
礼儀作法がきちんとできている、成績1000番の修習生と
礼儀作法がダメな、成績200番の修習生
であれば、前者を高く評価する。
礼儀作法は成績よりも優先する問題である。
2、話しているときの表情が良いかどうか
話の内容でウソをつける人は多いだろうが、表情でウソをつける人間というものは少ない。
他人と会話をしているときに、ニコニコとして楽しそうに話している人に悪人がいるようには思えない。
暗い表情で話をしている人に、明るい性格の人がいるとも思えない。
吉田の経験上、「目つきの悪い人間」「顔に険のある人間」が魅力的な性格をしていたことは、全くない。
その意味では、「顔」というものは大事なものだ。
美醜よりも、やはり、表情があって活き活きしているかどうかが大事である。

自分の過去を振り返ってみてくれたまえ。
小学校や中学校のクラスで、実際に人気があった女子は、
美人というより、表情が活き活きとした人ではなかっただろうか。
顔かたちが良くても、陰気だったり、いつも怒っているような人は、人気はなかったであろう。
これは、小学校や中学校に限らず、社会人になっても同じことなのだ。
キリリとした表情であるとか、活き活きした表情であるとか、良い表情の人間は面接で高く評価される。
多くの面接官が
「会った感じが大事だ」
「会ってみないとわからない」
と言うことが多い。
「会った感じ」の大部分は「表情」のことなのだ。
話しているときの表情を見るためには写真ではなく、面接をする必要があるのである。
いま一度強調しよう。
採用側が面接をするのは、面接をする理由があるからだ。
面接をする理由は、面接しなければわからないことがあるからだ。
面接しなければわからないこと、の大部分は「話しているときの表情」だ。
3、話しているときの声が良いかどうか
どういう声をしているかも大事である。
声の試験というものは、司法試験の科目にはないだろうが、
弁護士は、仕事をしているとき、つねに声を出さなければならない。
仕事をするうえで、良い声というものは、とても重要だ。
悪い例
小さすぎてか細い声
面接では不利である。物理的に、そもそも何を言っているのか聞こえない。
採用側の立場からすると、何回も「なんて言った?」「もう一度言って?」と聞き直さないといけないので、めんどうくさい。
また、声が小さい人は自分に自信がないように思える。
そして、たいていの場合、自分に自信がない人間が声が小さいのである。
聴きとれないくらい早口
人間はどうしても興奮すると早口になってしまう。面接では緊張しているので早口になってしまうということも理解はできるが、そうであるからこそ、意識して、ゆっくり話すと、落ち着いた度胸のある人間だ、ということをアピールできる。
ゆっくり話すということには、多くの利点がある。
1 ゆっくり話すと、それだけで他の人から落ち着いた大物だと思われる
2 ゆっくり話していると、考えながら話ができるので、話がまとまりやすくて賢く見える
3 早口でまくしたてるのは「攻撃的なふるまい」と相手に思われる。その一方、ゆっくり話していると、「親しみのあるふるまい」と相手に思われて信頼られる。

これらは、理屈ではなく、人間の本能に根ざした感情である。
ゆっくりと話した方が、非常に多くの場面でトクになることが多い。
努力して、ゆっくりと話そう。
語尾が消える人と、語尾まではっきり言う人
おそらく、多くの面接官が同じ意見だと思うが、話をしているときに、話の語尾まではっきりと言う人は意志強固で、しっかりしている人である。
一方で、語尾が小さくて「このように思います」なのか「このように思いません」なのか、イエス・ノーがよくわからない、という人は意志薄弱な人である。
良い声を出すためにはどうしたらいいのか?
よい声を出すための方法は以下のとおりである。
1 録音して自分の声を聞くこと
2 良い声の人を真似すること
3 面接の直前に発声練習をすること
吉田は高校時代に演劇部だったので、練習の前には必ず発声練習をしていた。
運動選手は運動する前に必ず準備運動するわけだが、それと同じで、演劇では、必ず発声練習から入る。
運動部の人なら理解できると思うが、準備運動をするのとしないのでは、その直後の運動能力に大きな違いがある。
発声も肉体の一部だから、発声練習をするのとしないのでは、全く声の発音や話しやすさが変わってくる。
吉田は、今でも、講演やセミナー活動をする直前には、発声練習をおこなう。
一度、発声練習をしてみてから、面接の練習をしてみよう。
話しやすさが全く異なる。
発声練習の方法には、いくつかあるが、お手軽でメジャーなのは、
アエイウエオアオ方式である。
口を大きくあけて、以下のように発音する。
アエイウエオアオ カケキクケコカコ
サセシスセソサソ タテチツテトタト
ナネニヌネノナノ ハヘヒフヘホハホ
マメミムメモマモ ヤエイユエヨヤヨ
ラレリルレロラロ ワエイウエヲワヲ
一音ごとに、あっ、えっ、いっ、うっ、えっ、おっ、あっ、おっ、と区切って発音すると切れがよくなる。
実際の発声練習はこんな感じでやっている。
やってみれば簡単なものである。
ラジオ体操みたいなものと考えよう。