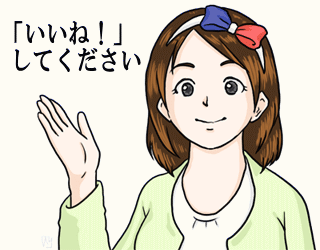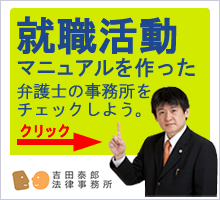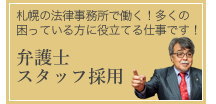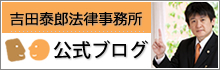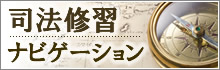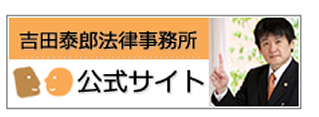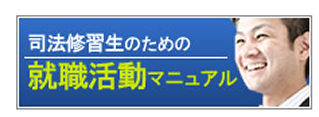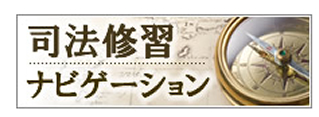グループ面接必勝法

なぜグループ面接に勝利するためには、
そもそも、なぜグループ面接をするのか、ということを考えないといけない。
グループ面接をするには、消極的な理由と、積極的な理由がある。
消極的な理由
グループ面接は、個別面接の足切りとしておこなう。
個別面接まですすむ人数を時間をかけずに絞り込む、という消極的な意味合いがある。
積極的な理由
では、グループ面接は、個別面接のたんなる劣化バージョンなのか?というと、必ずしもそうではないのだ。
吉田のように、できる面接官は、グループ面接をおこなう積極的な理由を考えているのだ。
グループ面接でないとできないことは、次の2点である。
・他の修習生が話しているときの態度を見る
・修習生同士でディスカッションしてもらう
他の修習生が話しているときの態度
じつは、グループ面接をする理由の半分は、他の修習生が話しているときの態度を見ることにある。
採用側が、今話している修習生しか見ていないと思うと、つい無防備な状態の自分の内心をさらけ出してしまうのだ。
とくに採用側が複数いる場合には、一人が質問をしている間、他の人は
「自分の話す番ではない状態の修習生の態度」
をかなり入念にチェックしている。
賢い修習生ならば、自分で
「なぜグループ面接というものが存在するのであろうか」
という本質論から考えて
「グループ面接でないと出来ないことがあるからではないだろうか?」
というところまで考えが及ぶものだ。
そういうふうに、自分で物事を考えることのできる人間こそ、優秀というのである。
パーな修習生の場合には、吉田が親切に教えてあげているのに
「それは吉田氏の独自の考えであって、今回受けるグループ面接も同じとは限らない」
などと、自分にとって都合の良い理屈をつけて信じないようだ…

表情のプラスとマイナス
マイナス…他の修習生の話を、いらいらしているような表情をしているとマイナス
忍耐力がなく、常に自分が中心でないと気がすまない性格だと思われる
マイナス…他の修習生の話に対して無関心な表情をしているとマイナス
他人のことに興味がない消極的な性格だと思われる
マイナス…あくびをしているとか、よそ見をしているとか、不真面目な態度だとマイナス
他人のことを下に見ていて、どうでもよいと思っていると見なされる
プラス…他の修習生の話に合わせて、あいづちを打っているとプラス評価
他人の話をちゃんと聞いている性格だと思われる。
プラス…他の修習生の話を聞いていて楽しそうとか、興味深そうな表情をしているとプラス評価
他者に対する関心がある積極的な人だと解釈される
グループディスカッション形式の場合
面接官がみているのはディスカッションの結論ではない
明らかにディスカッションの過程である。
面接時と違って、相手が同じ修習生の場合、わりと地が出てしまう
嫌われる態度
・安易に他の人の発言を否定する
・大声を出すなど攻撃的な態度を示す
・ディスカッションに積極的に参加せず沈黙している
・あくびをする、頬杖をつくなど不真面目な態度をとる
理由 弁護士の仕事の半分以上は「聞く」ことです。他人の話をちゃんと聞ける人間なのかどうか、は、とても大事なことです。
経験のある弁護士ならば、自分の性格と切り離して「聞く訓練」が自然と出来ているものですが、若い人の場合、「聞き方の授業」というものがないため、自分の性格がモロに出てしまうのです。
言うまでもなく、コミュニケーション能力は「話す」だけではなく「聞く」能力が必要なのです。
ディスカッションでは「何を話しているか」も大事ですが「他人の話をちゃんと聞いているか」ということも同じくらいに大事なのです。
好まれる態度
・ディスカッションの交通整理をして、司会進行役をする
・他の修習生の話を理解してその上に議論を展開する
・他の修習生の話を興味深く聞いている
・楽しそうにしている
理由 ディスカッションのテーマは、
・価値観や考え方によって結論が異なるもの
・複雑怪奇な案件に関するもの
・抽象的なテーマであって、どう議論していいのかよくわからないもの
のようなものが与えられることが多いです。
少なくとも、1+1=2のような、単純に結論だけそれぞれが言って終わり、ということにはなりません。
こういう、どうやったらよいのかよくわからないディスカッションこそ、
ディスカッションの細かい中身にすぐに飛びつくよりも、
「結論を出すためには、①②③④という4つの議論をおこなう過程が必要だ。では、まず①から検討しようか」
というような、ディスカッション全体を把握したうえで、ディスカッションの司会役ができる人が必要です。
こういう役割を自然とできる人が、真に優秀と言われる人なのです。
いきなりのディスカッションでも司会役がつとまるのは、一つレベルが突き抜けた知性があると言えます。
もっとも、そこまでできる人を期待するのは難しいところなので、通常は、他の修習生の議論をちゃんと聞いたうえで、理論展開ができるとか、
反論をするときでも、無下に否定するのではなく、やわらかく相手も同意せざるをえないように話をもっていく、他人の話に対して興味関心をもって聞いている、というようなレベルでもOKです。
グループディスカッションと言うと、なんだか難しそうですが、平たく言えば「ワイガヤ」というやつです。
昔、日本の高度成長期のころには、いろんな会社で、問題が発生するたびに、現場で人間が集まってきて「ワイワイガヤガヤ」と話し合ったものなのです。
そういう現場の「ワイガヤ」を仕切れるのが実力のある人であり、人望がある人、ということになったのです。
法律事務所にかぎらず、どんな会社でも働き出せば、未知の問題に対して現場の「ワイガヤ」が発生します。
その意味では、未知の問題に対して現場の「ワイガヤ」をまとめる能力というものは、組織全体の見地からして、とても必要とするものです。
まとめ
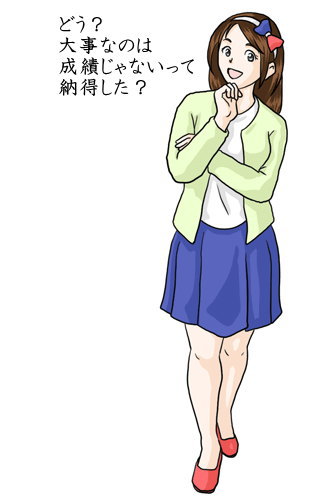
どうでしょうか。
採用面接では、司法修習生が考えている以上に、採用側というものは、いろいろと考えて選考をしているのです。
決して、司法試験の成績だけで全部決めてしまうような事務所はありません。
そんな事務所だったら、とっくの昔につぶれてしまっています。
弁護士吉田は、成績よりも人柄が大事だ、と言っています。
それは真実なのですが、かといって、それは甘いことを言っているのではありません。
むしろ、とても厳しいことを言っています。
つまり、弁護士吉田は、採用されないのは、あなたの人格が悪いからだ、と言っているのです。
決して、「司法試験の成績が悪いから落ちるんだ!」などと、責任転嫁をしないように。
あなたが良い人柄であって、それが面接官にも伝われば、成績なんて何番であっても合格します。
ですので、面接では、自分の良い面をきちんと伝えること。もし、人格が本当に悪いならば、まず人格をマトモに直すこと。
それが面接合格への早道です。